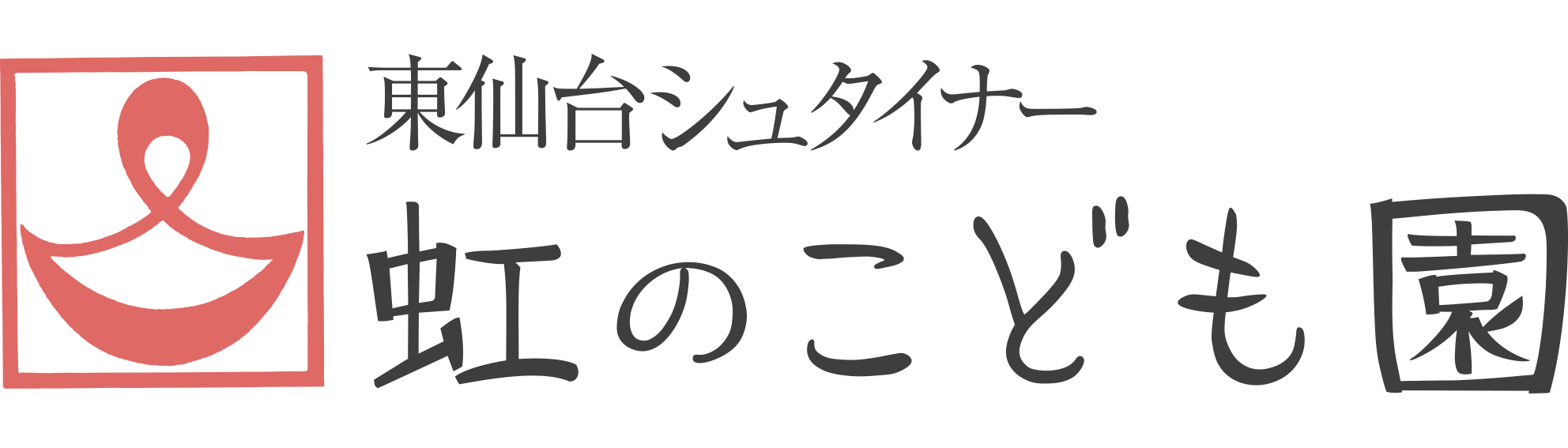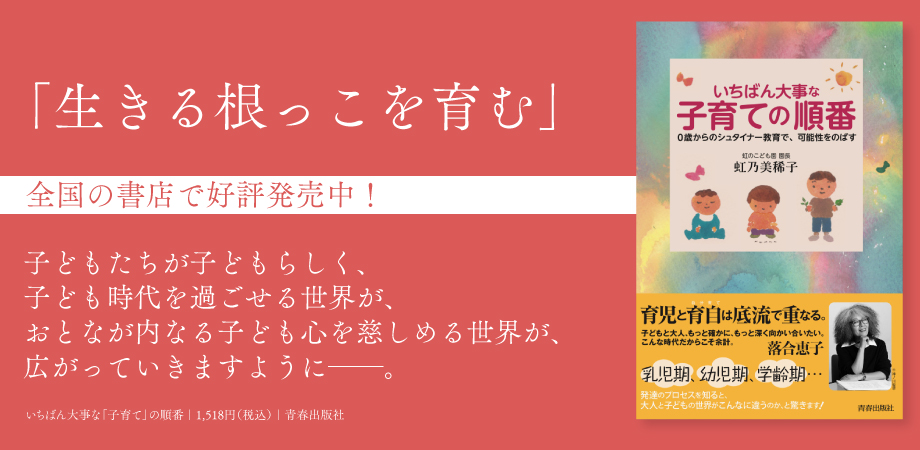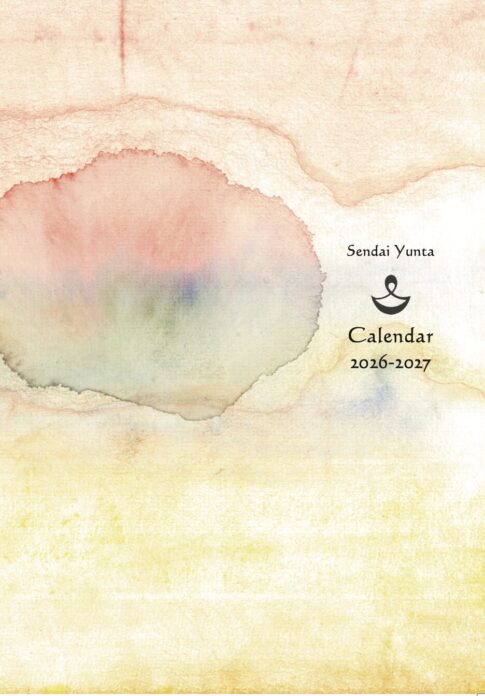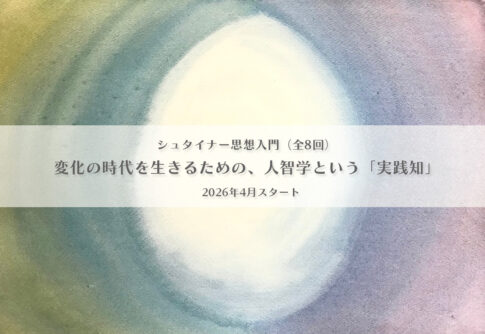夏休み、ひょんなことから大学の先生になっています。
仙台の某私立大学の1年生100名ほどに、発達心理学を教えることに。
本当は前期担当なのですが、夏休みの集中講義にしてもらいましたのでこの夏はちょっと忙しく過ごしています。
普段小さな人たちの「せんせい」として教室にいるので、大学で成人(今は18歳で成年)の人たちに教えるというのは少し緊張します。
そう話すと「普段から大人向けの講座慣れてますよね」と言われますが、いやいや全く違うんです!
何が違うというと、普段の講座は受講生の方々が積極的な意思を持ち、自らお金を払って参加してくださっていますが、大学の学生たちは単位取得のために半ば「義務として」机に座っています。
積極的な関心を示してくれるのはごくわずか。
広い教室の後方では、居眠りしている姿も、また友人と私語の止まらぬ姿も見られるわけです。
まあ、学生とはそんなもの。
自分だって学生時代は、遊ぶことにより注力していましたし。
教育系の大学でもないですから、そもそも「発達心理学」に興味を持ってくれる学生も一握りでしょう。想定内です。
それよりも、夏休みに私の都合で集中講義になってしまっているわけですし、仙台も例年をしのぐ猛暑の中、1限目から集まってくれる学生にエールを送る気持ちしかありません。
聞いてくれてありがとう!
せっかくの機会ですから、子どもと、それから自分の子ども時代に関心を少しでも持ってもらえたらうれしい。
もう少し先の未来に、親になる機会があるかもしれないことを、楽しみに感じてくれたらうれしい。
そんなささやかな願いを持って、慣れない教壇に立っています。
大学の講義ですから、シュタイナー教育の観点にも触れますが(それも貴重な機会!)、基本的には一般的な「発達心理学」について話さなければならなりません。
そのために私も改めて最新のことを学び直し。するといろんな発見があります。
30年前の学生時代に自分が学んだことに比べると、当然ながらだいぶ進化しており、シュタイナーが示唆していることにだいぶ近づいてきたな、同じことを言っているなという発見もあったりしてこれもまた面白いです。
例えば「生涯発達心理学」という観点。
生涯発達心理学とは、人間の受胎時から老年期までの生涯を通じて、どのような心理的特性が作用しているかなどを研究するものです。
かつての発達心理学では、成人期以降は単純に「衰退の時期」とされており、子どもと青年期までが研究対象でしたが、現在では年を重ねても経験から得られる知恵や判断力などの内面的変化や機能的な変化は「向上する」という面が発見されるようになりました。
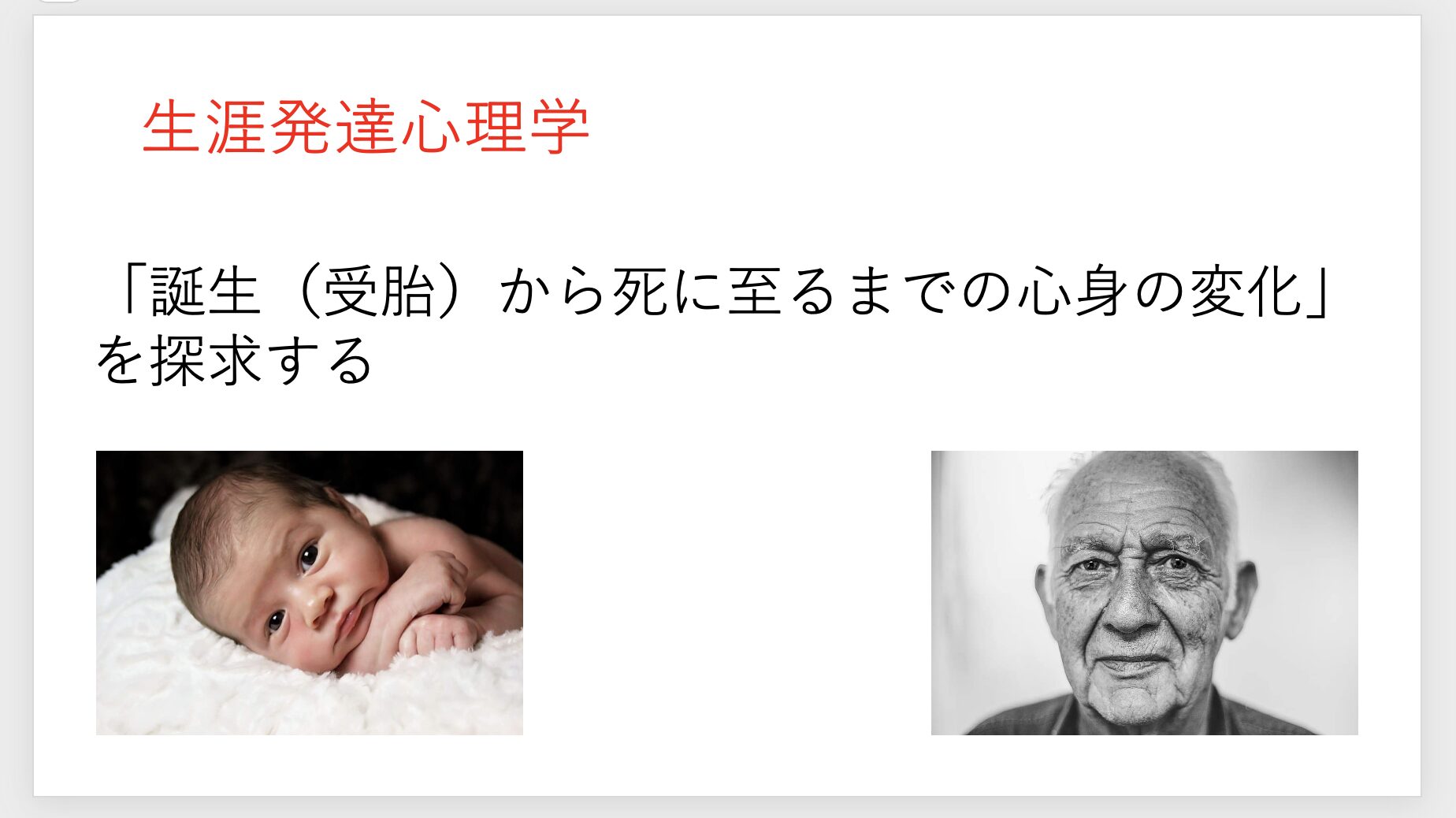
これは21歳を経ても7年ごとに人間は精神的にも成長を遂げていくというシュタイナーのバイオグラフィーの考え方に通じるものです。
もちろん、「成長しよう」とする「自我」の働きがあってこそのものですが。
そんなことも余談で添えながら話を進めていった初回は、講義を終えたら早速最前列で熱心に聞いてくれていた女子学生が、質問ですと駆け寄ってきてくれました。
私の経歴を知って、シュタイナー教育を事前に調べてみたとか。
「幼児には一切知識や情報を教えずに、生活体験だけを重視するんですか?」という質問に、
「例えば、知識や情報を教えないというのは、『どうして虹が出るの?』という子どもの質問に、虹が出る科学的理屈をそのままに説明するのではなくてね、、、」と話しました。
さあ、皆さんならなんと答えますか?
ー虹は、雨があがって喜んだおひさまが空に描いてるんだよ。
ーかみさまが世界に色をつける絵の具だよ
ー虹が出た時は、どこかで誰かが誰かのためにとても良いことをしたというしるしなんだよ。
この世界にやってきたばかりの子どもたちが、単なる科学的な仕組みを知るために、もっと想像力を携えて、世界を善だと感じられるように。世界を信頼することができるように。
その根っこを育てる時代が幼児期であるということをお話ししたら、目を輝かせて「とっても素敵ですね!」と喜んでくれました。
講義準備は大変ですが、この仕事引き受けてよかったなと心から思えました。
次回も楽しみに頑張ります!

文・虹乃美稀子
「小さな声が聞こえるところ」は新月・満月の更新です。
8月9日満月🌕は夏休みのため更新お休みいただきます。
次回は8月23日新月🌚の更新です。