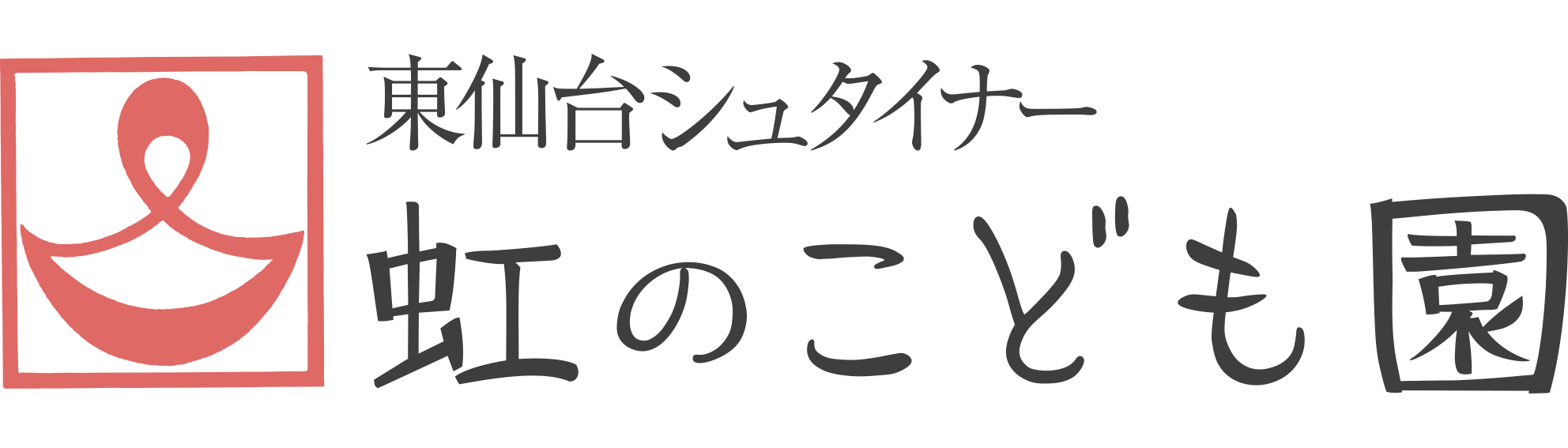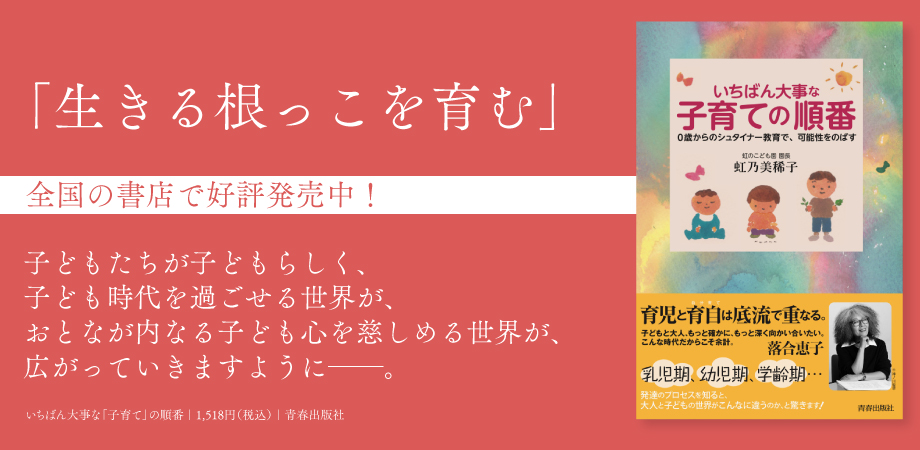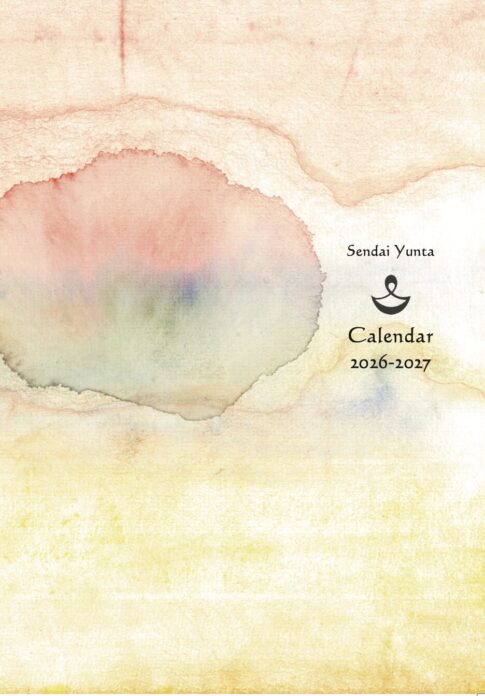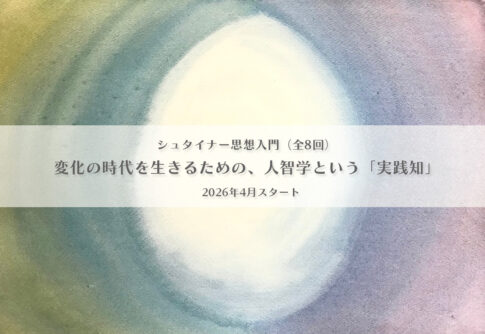今年も早々と真夏の暑さがやってきました。仙台も夏至前から30度を超える暑さとなり、年々異常気象が「ニューノーマル」になっていることを感じます。
子どもの頃から、夏は平和を語り継ぐ季節だと感じていました。
6月23日は沖縄慰霊の日。80年前の夏はこの沖縄の玉砕、各地での空爆、そして広島と長崎の原爆投下を経て、8月15日の終戦に至るまで日本列島は痛ましく筆舌に尽くしがたい戦禍を被り続けました。
仙台空襲(せんだいくうしゅう)は7月10日のことです。仙台の中心部を焼け野原にしたこの焼夷弾空襲は、およそ1400人もの命を一夜にして奪いました。しかし、この記憶を身近で語られる機会は地元においてもとても少なくなってきています。
そんなことを考えていたところ、地元の新聞で仙台市の施設である戦災復興記念館の資料展示室の入場者が伸び悩んでいるという記事を見ました。
特に、小中学生の利用がコロナ禍以降低迷しているそうです。

「貸切バスの利用料が値上がりしている」
「教科書に掲載されていない仙台空襲について学ぶ時間の余裕がない」など理由はいくつか挙げられていましたが、それと同時に、やはり戦後長い時間を経る中で直接の体験者が減っていき、語り継ぐ意志を持つ人がとても少なくなっているからなのではと思います。
自分が経験していないこと、しかも悲惨で辛い話を、あえて真摯に伝えていこうとするのはとてもエネルギーのいることです。
でも、私自身も子ども時代に本や漫画や映画にテレビ、さまざまなメディアを通して受け取っていたからこそ、戦争の愚かさ、平和の大切さ、その平和を生み出す責任は私たちひとりひとりにあることに気付かされたのだと思います。
そうしたメディアの制作側にいた当時の大人の人たちは、ご自身が体験した戦争時代の辛い記憶を背負いながら、傷を抉(えぐ)るような思いで、しかし伝えなければいけないという使命感のもとに発信を続けられた方もたくさんいらしたことでしょう。
戦争を知らない世代が大人の大半となった今、私たちはどんなふうに平和の尊さを、戦争の愚かさを伝えていけるのか。
世界を見渡せば、戦火は止まぬどころか広がる一方であり、平和は遠くなっていくようです。
幼児にはまだ社会問題を具体的に伝える年齢にはありませんが、小学生以降の子どもたちに、年齢に応じてどんな風に伝えていくことができるのか考えているこの頃です。
また、私たち大人もまた、そうしたことを知り考える機会をもっと持つことが大切だなと思う戦後80年目の暑い、暑い夏です。

文・虹乃美稀子
「小さな声が聞こえるところ」は新月・満月の更新です。
次回は7月25日新月🌑の更新です。