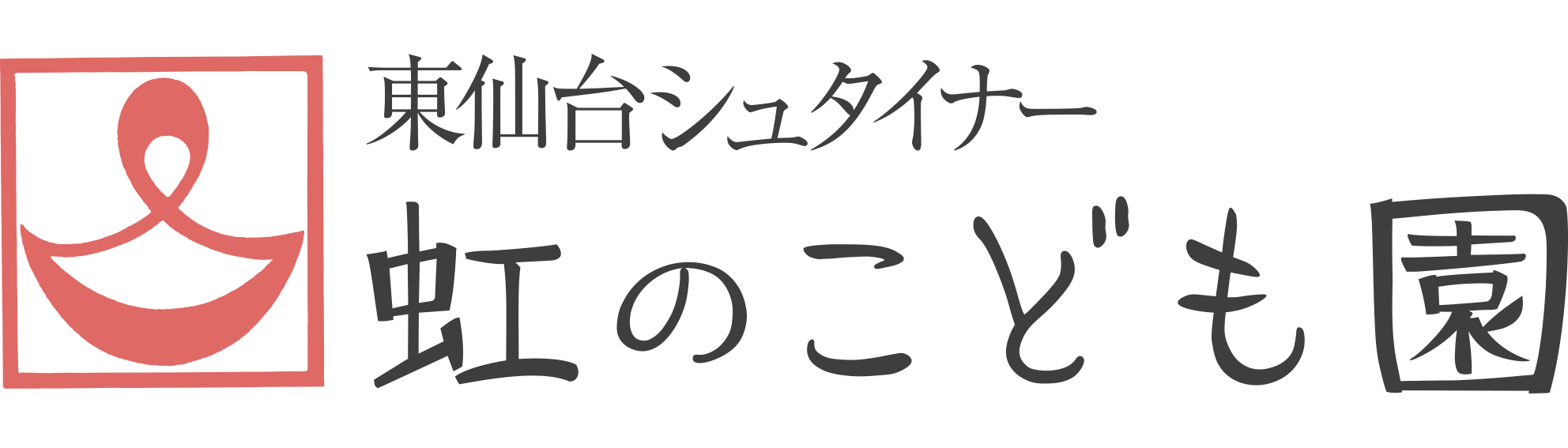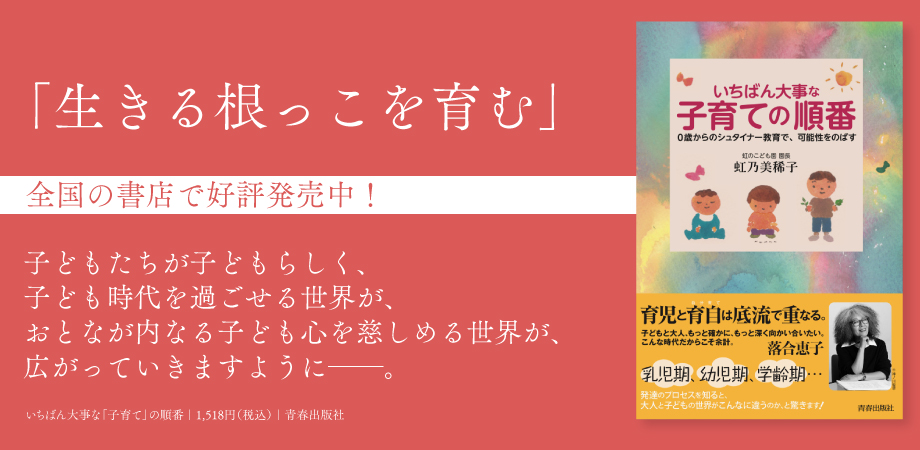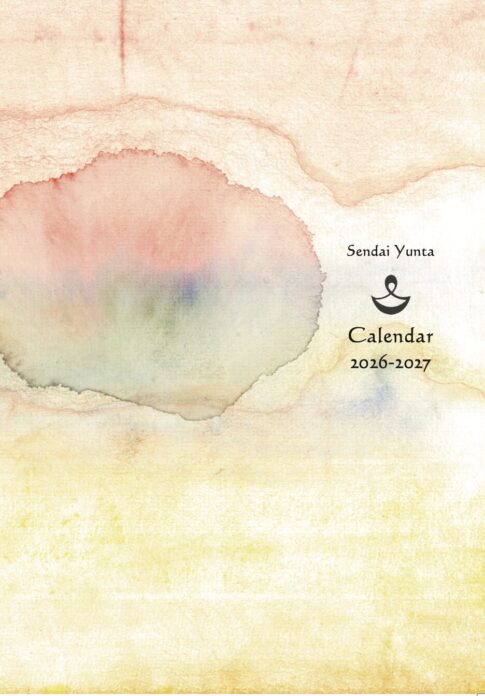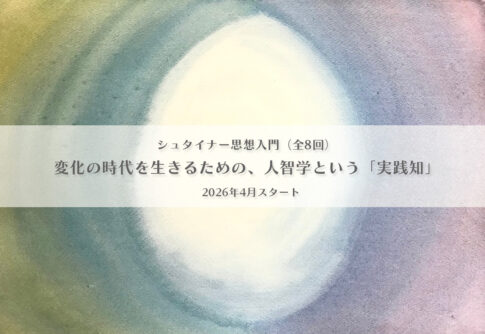20代の頃からなんとなく好きな作家に藤田嗣治(1886-1968)がいます。藤田は、日本生まれのフランスの画家であり彫刻家です。晩年はフランスに帰化し、洗礼も受けています。第一次世界大戦前よりパリで活躍していますが、おかっぱ頭に丸メガネという前衛的でファッショナブルな装いと共に、当時のパリでも人気を博していたようです。
その藤田は写真も撮るのが好きで、この夏東京のステーションギャラリーで写真と絵画の両方の展示があるというので行ってきました。

藤田の作風は猫と女性を得意な画題としています。そして日本画の技法を油彩画に取り入れているのも惹かれたところかもしれません。
私は若い頃、この藤田の猫でも女性像でもなく、秋田の祭りと暮らしを描いた世界最大級と言われる大壁画「秋田の行事」を見た時に一番感動しました。
さて、今回の展覧会は藤田の撮影した写真が絵画とともにたくさん紹介されているのが見どころでしたが、その中でひとつ印象に残った絵がありました。
それは《庭園の子ども達》という絵です。

この絵、庭園にいる割に何か不自然な気がしませんか。
1958年に描かれたこの《庭園の子ども達》はまるで宗教画のような空気を纏った作品ですが、実はこの絵は子ども達がソファに並んで当時最新のメディアであったテレビに釘付けになっている写真を元に描かれています。
その解説を読んで、どうりで!と思いました。
庭園にいる子ども達がそこにいる虫や鳥に興味を惹かれていたら、子どもの身体はこんなふうに静止していないはずです。
子ども達の視線も、生きたものを追っているようには見えず、何かを凝視していて身体は完全に受け身です。
現代ではテレビの他にもさまざまな動画配信がありますから、子ども達がこんなふうにスクリーンに釘付けになって凝視する時間は、この1950年代より比べ物にならないくらいに増えていることでしょう。
シュタイナー教育では子ども達の年齢が小さければ小さいほど、なるたけスクリーンを見せないで!と伝えています。
一生を生き抜く「身体」を育てている子ども時代は、身体を十分に使わないと育ちません。それには暮らしの中でもいかに身体を使っていくか、ということが大事なのですがスクリーンタイムは子ども達からその時間を全て奪っていくのです。
スクリーンに向かっている間、脳と目は過剰で一方的な刺激を受け続け子ども達は完全に受け身となります。スクリーンを見せていると子ども達が静かになるのは、興味を持って「学習」しているのではなく、過剰な刺激に感覚器官がいっぱいいっぱいになり、考えること、動くことが抑制されてしまうからです。
成長期の子どもたちにとって大切なことは「能動的に」動くこと。
繰り返しお伝えしてきたことですが、図らずもこの藤田の絵を見て、ああ、このスクリーン問題はすでに70年も前から始まっていたのだなと改めて実感しました。
日本にテレビが入ってきた時に少なくない大人が「テレビを見るとバカになる」と警鐘を鳴らしましたが、今はそんなことを言う人はいなくなってしまいました。みんな、テレビを見て育ってきましたからね。
私も見て育ちました。配信動画も、時々見ますし、動画講座も行っています。そして自分の集中力や思考力の低下も、感じています。。。
悩ましいですね。この問題、これからも考え続けていきたいです。
でも、展覧会はとても楽しかったですよ。
芸術の秋、また気分転換に美術館をふらりと訪ねたいと思います。
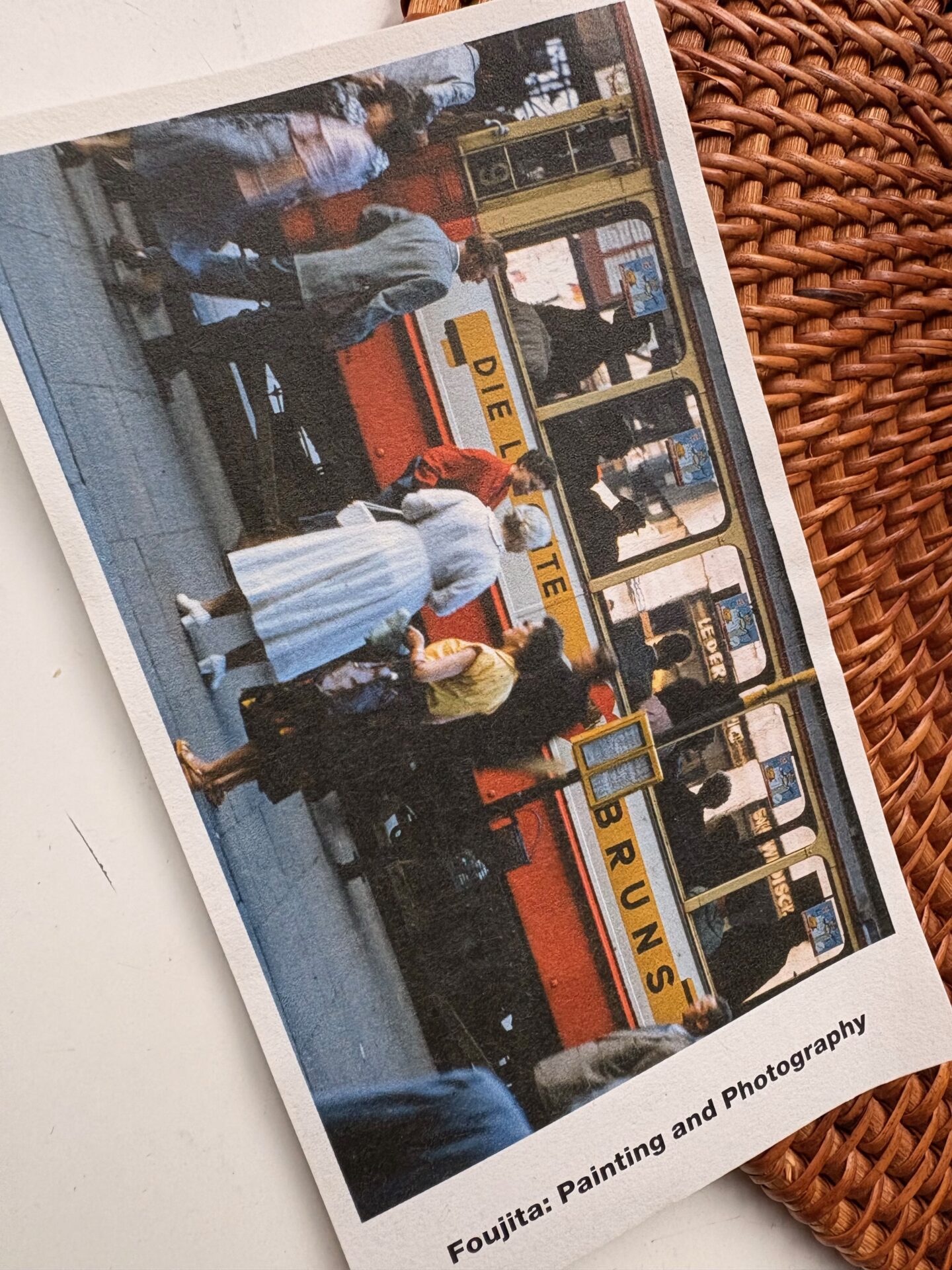
(文・虹乃美稀子)
「小さな声が聞こえるところ」は新月・満月の更新です。
次回は9月22日新月🌚の更新です。